まいどおおきに!Akidou(@Akidou123)です!
このページをご覧になられた方は、こういった疑問や悩みをお持ちじゃないですか?
ガンプラを始めた人が必ずやってみたくなるのが『塗装』。雑誌の作例やSNSなどの投稿作品でカッコいいと思った作品がとても上手な塗装だったら、自分も同じような作品を作ってみたいと思いますよね。
でも、初心者にとって模型の『塗装』は「難しい」という印象を持つ人の方が多いと思います。(僕も最初はそうでした。)
この記事では、なんだかんだでモデラー歴10年になる僕だから分かる、初心の気持ちと蓄えた知識で、実験と写真を交えて塗装の『筆塗り』について解説していきます。
ページ分割していますが、長い記事となるので、下記ページ別にリンクを用意しました。観たいページをご覧ください^^
- 1ページ目:塗装をする方法の説明(筆塗り、ペン塗り)(このページです)
- 2ページ目:塗装をする方法の説明(スプレー塗装、エアブラシ塗装)
- 3ページ目:筆塗りに必要な道具って何?(筆、塗料、パレット)
- 4ページ目:筆塗りに必要な道具って何?(うすめ液、他にあるといいもの)
- 5ページ目:実際に塗ってみよう
- 6ページ目:まずは練習から~ガンプラに塗る前に
- 7ページ目:実践してみた違いを見てみよう~まずは筆塗りを始めよう
塗装をする方法

そもそも「塗装」ってどういう方法があるのか?というところを簡単に説明します。
ガンプラ(プラモデル)の塗装には主に次の方法があります。
- 筆塗り
- ペン塗り
- スプレー塗装
- エアブラシ塗装
様々な表現方法がある「塗装」ですが、基本原則的にこの4種類の方法を知っていれば、応用が利くので知っておいて損は無いと思います^^
では、順番に簡単な説明をしていきます。
昔から親しまれている『筆塗り』
『筆塗り』は皆さんも知っている「筆」を使った塗装方法です。
プラモデルが流通した初期の頃から、今も長く愛用される塗装方法で、初心者が気軽に塗り始める事が出来るうえに、プロの方でも筆塗りオンリーで活躍されている方々もいらっしゃいます。
下手な人が塗ると下手な塗装になるけど、上達すると筆塗りにしか出来ない表現方法などもあるので、入り口から出口までずっと広いイメージなのが、『筆塗り』です。(最近流行りのアニメ塗りも言わば筆塗りの一種ですね)
筆塗りは作業環境に左右されにくく、いくつかの道具を揃えるだけで「安価に」かつ「簡単に」塗装が出来るのが最大のメリット。また塗料を調色出来るので、好きな色を作り出すことも簡単に出来ます。
その一方で、慣れるまでは色ムラが出やすかったり、筆の扱いに慣れる必要があったりというデメリットも。
それでも、昔から初めての塗装は『筆塗り』という方も多いように、一番最初に塗装をするなら『筆塗り』はオススメです。
この記事は『筆塗り』編なので、揃える道具などについては後述します。
2000年前後から今でも人気の『ペン塗り』
これは主にガンプラに限るかも知れませんが、メーカーから市販されている「ガンダムマーカー」を使った『ペン塗り』という方法もあります。
僕の記憶が確かなら(懐かしいフレーズ)・・・、1997年辺りからガンダムマーカーの初期版があったかと思います。僕が中学生あたりで友人とガンプラを作るのにガンダムマーカーで塗ったりしていた記憶があるので。
その頃はあまり塗膜も強くなく、あまり良い印象は持てませんでしたが、今のガンダムマーカーは改良に改良を重ね、様々な種類のものが販売されています。
『ペン塗り』のメリットは筆塗りよりも必要とする道具が少なく、「ガンダムマーカー」があればすぐに塗装を楽しめます。ペンタイプなので、普段使っている筆記用具の感覚で塗装が出来るのも初心者にとっては簡単ですね。
デメリットは、「ガンダムマーカー」として購入する為、色が限定されているということ。様々な種類(水性や油性など)や色(基本色やメタリック色など)が発売されているとは言え、それでも通常の塗料と比べて「決まった色」でしか塗ることが出来ません。
とは言え、簡単に塗装が出来ることから、「部分塗装」と呼ばれる完成形を目指す人には取っ付きやすい方法です。
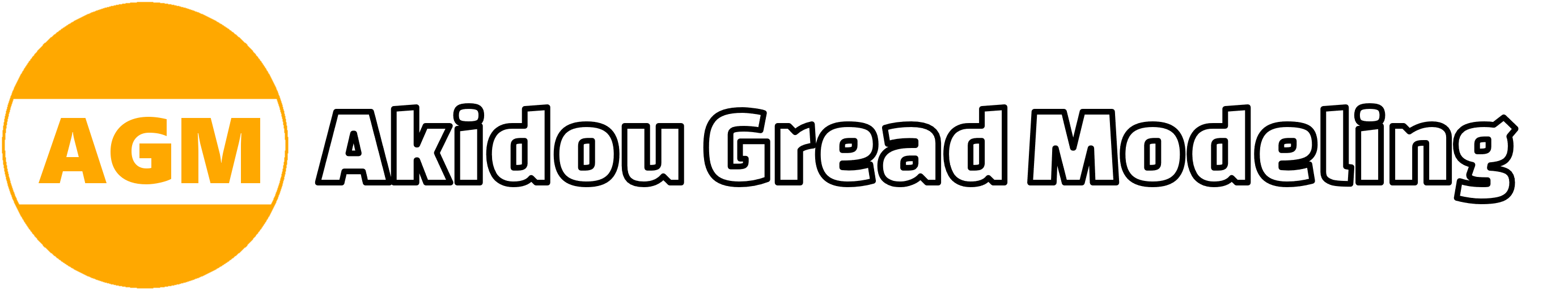

![[TEMLUM] プラモデル 塗装 モデルペイントセット クリップ 塗料工具 塗装スタンド/ベース 塗装筆 デカールスキージー 面相筆 スポンジ筆 塗料皿 スポイト 調色スティック 塗装セット 塗料皿 61点セット プラモ フィギュア 道具 模型 ホビー](https://m.media-amazon.com/images/I/51gxB4D7mZL._SL160_.jpg)


















コメント